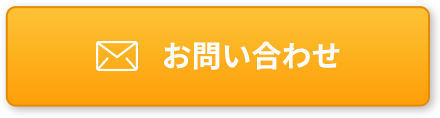相続コラム
相続税の計算方法を詳しく解説!自分で申告する際の注意点も

「自分が亡くなった際の相続において、どれくらいの相続税がかかるかどうかを確認したい」
「親が亡くなって相続をすることになったけど、相続税がかかるかどうかを確認したい」
いろいろな事情により相続税の計算が必要となる場合があります。相続税の試算は簡単にでもしておいたほうが良いのです。
その理由を、相続税の計算方法と一緒にお伝えします。
相続税の計算方法を解説

相続税額はどのように計算をするのでしょうか。 相続税額は、主に以下の6つのステップに分けて計算をします。
- 1遺産総額を計算する
- 2法定相続人の数を確認する
- 3遺産の総額から基礎控除額を引く
- 4課税遺産総額の計算をする
- 5相続税の総額を計算する
- 6相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
- 7各相続人の相続税納付額を計算する
計算方法は非常に煩雑であり、専門知識のない素人が個人で行うことは困難です。
ただし、相続税の申告・納税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合にのみ発生します。
そのため、もし基礎控除額を超える遺産がない場合には、3つめのステップで終了して問題ありません。
STEP1:遺産総額を計算する
まず、被相続人の遺産総額を計算しましょう。一般的に、遺産の総額は被相続人となる人が有している遺産を合計したものとなります。
遺産の中には株式のように、時期によって値上がり・値下がりするようなものも含まれますが、原則として被相続人が亡くなった日の価格を基準として考えます。
また、不動産のように鑑定をする目的や人によって価値が異なるものもありますが、 相続税上は「財産評価基本通達」に従って計算をします。
遺産総額の計算方法について、代表的な物をいくつか取り上げてみました。
- 預貯金は利息も含めて死亡時の残高で計算する
- 自動車は中古車買い取り業者の買取価格で計算する
- 土地や路線価または固定資産税評価額をもとに、どのように道路と接しているか・不動産の形状など土地の事情を踏まえて計算する
- 建物は固定資産税評価額によって計算する
- 上場株式は一定期間の平均株価からもっとも低いものを計算する
- 非上場株式は会社の財務状況から計算する
※相続税の中でも不動産の価格を最大80%下げられる、小規模宅地の特例はこの段階で計算します。
課税対象となる財産・非課税となる財産
相続税の課税対象となる財産は、現金・預貯金、株式や債権等の有価証券、土地・建物等の不動産、書画骨董等亡くなった人が所有していた財産です。
また、そのほかにも生命保険金や死亡退職金などのみなし財産、相続開始前3年以内に贈与した財産、相続時精算課税制度の適用となる贈与財産なども対象となります。
一方で、非課税となる財産として、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税額、債務、葬儀費用等があげられるので覚えておきましょう。
STEP2:法定相続人の数を確認する
基礎控除額の算定にあたって、まず法定相続人の数を確認しなければなりません。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを指します。
法定相続人になる人は被相続人の配偶者と被相続人の血族であり、血族相続人には以下のように相続順位が定められています。
常に相続人となる人:配偶者(正式な婚姻関係がある人)
第一順位:子(養子、非嫡出子、胎児を含む)
第二順位:直系尊属(子がいない場合は父母、父母がいない場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(子も父母などもいない場合)
第一順位から第三順位の相続人は、上位の人が相続した場合において下位の人は相続できません。なお、相続人が死亡している場合にはその人の子が相続人となることを覚えておきましょう。
STEP3:遺産の総額から基礎控除額を引く
遺産の総額が求められたら、総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は以下の計算式によって求められます。
3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)
たとえば、父が亡くなって、母・子2人で相続した場合の基礎控除額は次のようになるでしょう。
3000万円✕(600✕3)=4,800万円
なお、代襲相続が発生したことにより相続人が増えて基礎控除額が上がるようなケースがあるほか、養子には基礎控除額計算上の上限(実子なし:2人・実子あり:1人)が定められている点にも注意が必要です。
■関連記事
STEP4:課税遺産総額の計算をする
つづいて実際に課税される遺産の総額である、課税遺産総額を計算します。 課税遺産総額は、以下の式でもとめられます。
遺産総額ー基礎控除額
基本的に遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税を納めなければなりません。
ただし、小規模宅地等の特例を利用する場合には、宅地を80%評価減したことで基礎控除額を下回り相続税の納税が必要なくなる場合があるでしょう。
また、相続税の納税が必要なくなる場合でも、相続税申告は行なわなければならない点に注意しましょう。
STEP5:相続税の総額を計算する
相続人全員で納めるべき相続税の総額を計算します。
課税遺産総額に対して、いったん法定相続分で相続した場合の仮の税額を計算します。
この段階では、遺産分割でどのような結果になったかなどは問われません。この仮の税額を求めるときに、相続税の速算表が用いられます。
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
- |
|
1,000万円超から3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超から5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超から1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超から2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超から3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超から6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
参考までに、法定相続分どおりに相続した場合の相続税目安は以下の通りです。(配偶者がいる場合)
| 資産総額 | 相続人 | ||
| 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | |
| 4,000万円 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
| 1億 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
※配偶者の税額軽減は配偶者が法定相続分(1/2)どおり取得し、税額軽減を適用したものとして算出しています。
STEP6:相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
次に相続税の総額で求められた額を、実際の相続割合で分け直します。
法定相続分は遺産分割の目安を示すもので、実際にこの割合通りにきっちり分割を行なうものではありません。
たとえば、長男は母親の面倒を見ることを条件に自宅を相続する、という遺産分割協議がされると、実際に相続する割合は長男の方が多いということもあるでしょう。
のような遺産分割の具体的内容を反映するために、相続税の総額を、実際の相続割合に応じて分け直します。
STEP7:各相続人の相続税納付額を計算する
最後に、各人の相続税納付額を計算します。 この段階で考慮されるのは、配偶者控除や未成年者控除などの、個人ごとに適用される控除や、孫や受遺者などが相続財産を受け継いだ場合の2割加算などです。
また、配偶者は1億6,000万円または法定相続分までは課税されないという税額軽減の制度を利用できます。ただし、配偶者と被相続人の年齢が近い場合には、配偶者が亡くなったあとに相続が発生することになるので注意しましょう(二次相続)。
ひとつひとつの相続では有利な制度も、全体としてみると不利になるようなこともあるので、二次相続などを考慮した相続税対策を検討することが大切です。
相続税の試算をした方が良い理由
相続税の試算をした方が良い理由としては次のような理由が挙げられます。
- 1相続税の回避・軽減のための方策を練ることができる
- 2納税のための遺産分割をスムーズに検討できる
相続税の回避・軽減のための方策を練ることができる
相続が生じるとわかった段階で相続税の試算をしておくことで、相続税の軽減・回避する対策が必要かどうかを把握しておくことができます。
基礎控除額以下の遺産であれば相続税はかかりませんが、相続税がかかる基礎控除額のギリギリのラインにある場合には、生前の相続税対策によって課税を回避できる可能性があります。
また、相続税がかかることが確実である場合にも、できるだけ相続税がかからないようにすることもできるでしょう。
相続は親族内でトラブルに発生しやすいため、相続税の試算はもちろんですが、資産の整理や遺言書の作成なども着手しておくこともおすすめです。
スムーズな納税のための遺産分割を検討できる
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行なう必要があります。
10ヶ月という期間だけ示されると時間が十分にあるように思えますが、実際には亡くなって一定期間は相続の話をしない(基本的に四十九日法要まで)、遺産の調査に時間がかかる、遺産分割に時間がかかる、ということもあり、相続についての話し合いや準備をするにはあまり多い時間とは言えません。
時間が無くなった段階で税理士に依頼した場合、特急料金が必要となるケースもあります。事前に相続税の試算をしておくことで、スムーズに進む可能性が高まります。
また、相続税は原則として金銭を一括で支払う必要があり、相続した物を納付する物納や、数回にわけて納付する延納は例外的なものになります。
相続税の試算ができていれば、相続税の納付金の確保などを考慮したうえで遺産分割をすることが可能です。
相続税がかからなくても申告は必要になる
控除・非課税の特例を利用でき、相続税がかからない場合でも相続税申告は必要です。
たとえば、配偶者控除(配偶者の税額の軽減)・小規模宅地等の特例・未成年者控除・障害者控除などを受けられる結果、相続税はかからないという場合があります。
この場合でも、相続税の基礎控除額を超えているのであれば、相続税の申告をする必要があります(相続税申告の中で、これらの制度の利用をする)。
相続税の基礎控除額を超えている可能性がある場合には、相続税の試算をしておくべきでしょう。
相続税を自分で計算・申告する際の注意点

相続税の計算や申告を自分で行う際は、以下の3つの点に注意が必要です。
配偶者控除は申告が必要となる
相続税には、「配偶者の税額の軽減」という制度があります。この制度では、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となる財産額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されません。
また、仮に相続財産が1億6,000万円を上回った場合でも配偶者の法定相続分までであれば、相続税は課税されないこともおさえておきましょう。そのため、この制度を使えば配偶者にかかる相続税はほぼ無税になるといえます。
注意点として、この制度を利用するためには被相続人の住所を管轄する税務署に相続税申告書を税務署に提出しなければなりません。また、「被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内」に手続きをする必要があるので忘れずに済ませておきましょう。
申告が必要な理由としては、配偶者控除が適用される金額は、配偶者が実際に受け取った財産額をもとに算出されるため、相続税の申告書がなければ判断できないことが挙げられます。
養子縁組をしている場合は上限に注意
先に軽くお伝えしたように、養子は相続人となれる一方で、基礎控除額の計算においては以下の上限が定められています。
- 被相続人の実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含める
- 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含める
(※養子の数を法定相続人の数に含めることにより、相続税負担を不当に減少させると考えられる場合、その原因となる養子の数は上記の養子の数に含めることができない)
ただし、以下のいずれかの要件に当てはまる場合には養子であっても実子とみなされます。
- 1被相続人との特別養子縁組によって被相続人の養子となっている場合
- 2被相続人と配偶者の実子で被相続人の養子となっている場合
- 3被相続人と配偶者が結婚する前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、
被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった場合 - 4被相続人の実子、養子または直系卑属が既に亡くなっているか、相続権を失ったことにより、
その子どもなどに代わって相続人となった直系卑属である場合。(直系卑属とは子どもや孫のことを指す)
申告内容を誤るとペナルティが科される
相続税には複雑な計算が伴うことから、過大・過小申告してしまうケースも少なくありません。過大申告をしてしまった場合、本来支払う必要がなかった税金を納めてしまうことになります。
一方、過小申告した場合は追徴課税が必要となり、本来の税金よりも高く支払う可能性が出てくるでしょう。相続税の申告をする際は、申告内容に誤りが出ないよう、計算ミスをしないようにすることはもちろん、書類の不備がないように気をつけることが大切です。
期限内に手続きをする必要がある
相続税に関する手続きにはさまざまな種類があるほか、それぞれに期限が設けられています。すべてのスケジュールを自分で把握・管理する必要があるため、それ相応の労力と時間を要することになります。
もし期限を過ぎてしまうと、控除や軽減の制度が受けられなくなるほか、ペナルティが科される恐れがあります。
そのため、もし相続税に関する手続きについて不安がある場合は、早い段階で専門家に相談するようにしましょう。
相続税に関する悩みを相談するなら
このページでは、相続税の計算方法について、相続税の試算をしておいたほうがいい理由とともにお伝えしました。相続税がかかる場合の事前の対策や、被相続人がなくなった場合に相続税申告をしなければならないか、などで、相続税の計算を検討しておくことは良いことです。
ただし、相続税は非常に難解であり、安易に計算をすると手続きをスムーズにすすめられなかったり、損失を被ることがあります。相続税が発生するような相続では、相続税申告のみならず、不動産の相続登記や、株式の移転・事業承継などの様々な事項を考慮することが必要でしょう。
そのため、相続税の申告を自分で進めることに不安を感じている場合は、税理士に相談してみるのもひとつの手です。
相続税に特化している数少ない「川口相続税サポートセンター」では、月50件以上の相続相談を受けている実績があります。過去の事例から照らし合わせて提案ができるのが魅力です。相談は無料でできるため、もし不安な点が少しでもある場合は、この機会にぜひ一度お問い合わせください。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など