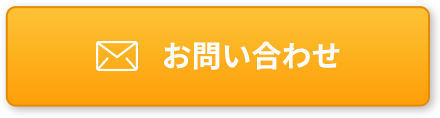相続コラム
相続税の未分割申告とは?デメリット・注意点や計算方法を解説

相続税の申告は遺産分割協議を行ってから申告することがほとんどです。
しかし、中には遺産分割協議がうまくいかず、調停・審判に進んでしまうこともあるでしょう。万が一調停が必要となった場合は非常に長い期間かかることが想定されるほか、10ヶ月の相続税申告の期限に間に合わなくなることも少なくありません。
このような場合には、遺産分割協議をしないで相続税申告を行う必要があり、遺産分割協議が整わない状態で行う相続税申告のことを「未分割申告」と呼んでいます。
そこで、今回の記事では相続税の未分割申告の概要をはじめ、デメリットや注意点についてもお伝えします。
そもそも相続税の未分割申告とは何か、計算方法やデメリット・注意点はあるのかどうかを知りたい方はぜひチェックしてみてください。
相続税の未分割申告とは?
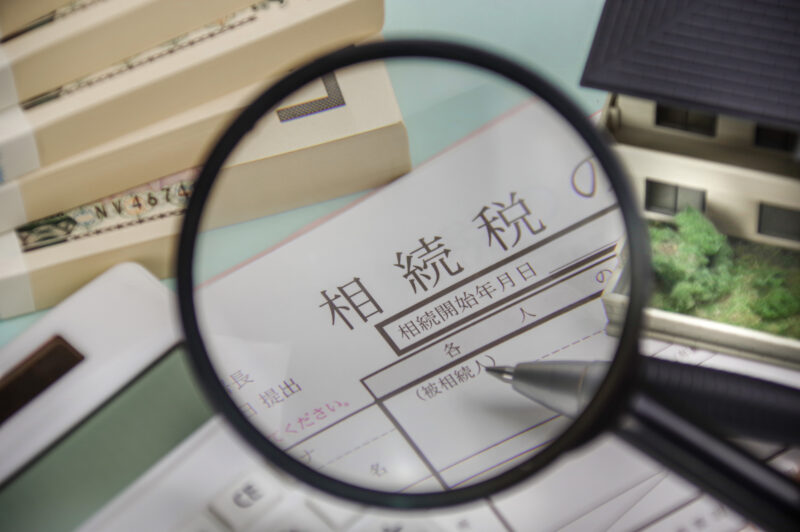
相続税の未分割申告とは、遺産分割をしないで仮の計算をして相続税申告をするものです。
相続税の申告期限は10ヶ月であるため、遺産分割の協議がスムーズに進まなければ調停・審判と法的な手続きが必要となります。そのため、申告期限に間に合わない恐れが出てくるでしょう。
このような事情があったとしても、相続税の申告期限は基本的に延長ができません。申告期限を過ぎてしまうと、翌日から延滞税・無申告加算税が課されてしまいます。 そこで例外として利用できるのが、相続税の未分割申告です。遺産分割が終わったあとに、相続税を払いすぎた相続人は、更正の請求をすることで、払いすぎた部分を取り戻すことが可能です。
相続税の未分割申告をするデメリット・注意点

相続税のみ分割申告をする際の注意点・以下のデメリットや注意点があります。
【相続税の未分割申告のデメリットと注意点】
- 配偶者の税額軽減が適用できない
- 非上場株式・農地などの納税猶予が適用できない
- 相続した財産で物納することができない
- 小規模宅地等の特例で宅地の評価減ができない
- 特定計画山林の特例を受けることができない
- 遺産の全部を納税に充てることができない
配偶者の税額軽減が適用できない
相続税を分割申告した場合、配偶者の税額軽減が適用できないケースがあります。配偶者の税額軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈によって財産を得た場合に、以下どちらか多いほうの金額までは配偶者に相続税がかからない制度のことです。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
税額軽減が利用できれば、相続税が発生する多くのケースで配偶者は納税する必要がなくなります。
しかし、この制度を利用する前提として、遺産分割手続きが終わっていることが条件となるため、遺産分割が終わっていない未分割申告の際には、この制度の利用が適用されません。
遺産分割が終わった後に申告書の再提出が必要
未分割の状態で相続税の申告書を提出した場合、遺産分割協議がすべて終わった後に申告書を再度提出しなければなりません。その際、当初の申告より相続税の納税額が増えたか、減ったかによって提出書類が下記のように異なります。
- 当初より相続税の納税額が増えた→修正申告書
- 当初より相続税の納税額が減った→更正の請求書
修正申告書を出した場合は差額の相続税を納める必要があるほか、更正の請求書を出した場合には納め過ぎた相続税の還付を受けられます。なお、更正の請求書については記載事項に誤りがあったり、添付書類が不足していたりすると手続きが行われない点に注意しましょう。
非上場株式・農地などの納税猶予が適用できない
非上場株式および農地の納税猶予は、相続税の納税によって事業や農業の継続が困難になることを避けるために設けられた制度です。
非上場株式の納税猶予では、非上場株式(オーナー企業の株式)を相続して事業を継続する場合において、一定要件を満たした場合に非上場株式にかかる相続税の納税が猶予されます。
また、農地の納税猶予では農地を営んでいた被相続人から農業の用に供されていた農地等を相続し、その農地において農業を続ける場合には、一定の要件下で相続税が猶予されます。
これらの制度を利用する場合、遺産分割協議が済んでいることが求められるため、遺産分割協議が調わず、農地の後継者が決まらない状態である未分割申告では利用できません。
相続した財産で物納することができない
未分割申告をした場合に、相続税が支払えないからといって物納をすることができないのもデメリットといえます。というのも、相続税の納付は現金で一括で行なうのが原則だからです。
しかし、現金で支払えない場合には、相続した物を納付して支払う物納という方法が認められています。物納をするための条件の一つとして、管理処分不適格財産ではないことが必要です。
遺産分割が終わっていない場合を含めて、所有権が誰のものになるか決まっていない場合は、管理処分不適格財産となるため物納ができません。
小規模宅地等の特例で宅地の評価減ができない
相続財産に不動産がある場合、小規模宅地等の特例による宅地の評価減が見込めます。
小規模宅地等の特例を適用することで、居住用宅地であれば240㎡まで80%減額、不動産貸付事業宅地で200㎡まで50%の減額が可能です。 相続財産の価値の大部分が宅地であるような場合、この特例を利用することで相続税の大幅な減額が期待できます。そのため、居住用の不動産をもっている場合にはぜひ使いたい特例といえるでしょう
ただし、この特例を利用するためには同居の親族が承継したことを明らかにする必要があります。そのためには当然、遺産分割を済ませなければなりません。遺産分割が済んでいなければ、この制度を利用することはできず、一度未分割申告をした上で相続税を支払い、後に更正の請求をすることになります。
特定計画山林の特例を受けることができない
遺産に山林がある場合に、その森林が特定計画森林にあたる場合には、通常の方法により算定した価格の95%の割合に評価を減じることが可能です。
特定計画山林の特例を受けるためには、遺産分割協議が終わっていることが前提条件となります。そのため、遺産分割が済んでいない場合にはこの特例を受けることができず、未分割申告をして、あとから更正の請求をする必要があります。
遺産の全部を納税に充てることができない
遺産を未分割のまま相続税申告をする場合、仮の申告が必要となることは先にお伝えした通りです。その際に相続税を納める必要がありますが、税額軽減の特例が適用できないことから、一般的には多額の納税資金を払わなければなりません。
しかし、遺産分割が済んでいなければ預金を引き出すことができないのはもちろん、預金や不動産を担保に納税資金を借り入れることも困難です。よって、遺産を納税資金に充てることはできず、手持ちの資金で納税資金の支払をしなければならないのはデメリットといえます。
なお、万が一納税資金が不足する場合には「仮払制度」が利用可能です。仮払制度によって遺産分割前の預金を引き出せますが、相続人ごとに引き出せる割合が定められているほか、同一金融機関からの引き出しは150万円が上限となっている点に注意が必要です。
未分割の遺産から得られる不動産所得の取り扱いについて
アパートやマンションをはじめとした賃貸物件が未分割である場合、遺産分割が終わるまでは相続人全員の共有の財産として扱います。そのため、未分割の賃貸物件から得られる不動産所得は法定相続分で分け合うことになるでしょう。また、万が一相続人の誰かが収益を管理していたとしても、不動産所得として利益を得ている以上、相続人全員が所得税の申告を行わなければなりません。
また、遺産分割の結果、法定相続分と異なる割合で当該物件を相続することになったとしても不動産所得の申告を遡って修正することはできない点に注意が必要です。
未分割申告の計算方法
未分割申告をする場合、法定相続分に従って計算することになります。 相続税の課税価格の計算は次のような流れで行います。
- 各人が相続によって得た課税価格の計算(実際に得た価格ではなく法定相続分に従って計算する)
- 各人の課税価格を合計して課税価格の合計額を計算
- 基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算
- 法定相続分に従って取得したものとして取得金額を計算
- 取得金額に応じて「算出税額」を計算
- 各人の算出税額を合計して「相続税額の総額」を計算
- 「各人ごとの相続税額」を、財産を取得した課税価格に応じて割り振って計算(このときに上述したように法定相続分に従った課税価格に応じた計算をする)
- 「各人の納付税額」の計算
本来、課税価格の計算をするためには、遺産分割を行い取得した遺産を確定させなければなりません。しかし、未分割申告においてはこの部分を法定相続分で計算して手続きをすすめることになります。
つまり、未分割申告ではいったん仮の申告を行った後、分割が決まった時点で修正申告や更正の請求を行うことから、実質2回分の申告が必要です。その他の相続手続きを行いながら遺産分割協議を調え、2回の申告を正しく行うことは相続人にとって大きな負担のかかる作業であることは言うまでもありません。
未分割申告の計算を含め、申告作業を行う際は税理士をはじめとしたプロに依頼することをおすすめします。
未分割申告の方法
未分割で相続税を申告する場合、特例を適用せずにいったん「仮の申告」を行う必要があります。仮の申告を行うことで、期限後に遺産分割協議が整った段階で特例の適用が認められます。
ここでは未分割申告の方法について、詳しく見ていきましょう。
「分割見込書」を提出する
未分割の状態で相続税の申告を行う場合、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう。「分割見込書」を添付することで、あとから更正の請求が可能となります。万が一添付を失念してしまうと期限後申告とみなされるほか、特例の適用が認められない恐れがあるので注意が必要です。
なお、分割見込書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
参考:[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁
また、分割見込書を提出した場合、更正の請求期限は分割が行われた日から4ヶ月以内です。期限内に更正が行われないと、税額の還付を受けることができません。
期限3年に間に合わない場合も申請すれば猶予がある
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したにもかかわらず、遺産分割調停・審判が長期化し3年以内で解決しないケースも稀に見受けられます。
なんからの事情で相続税の申告期限の翌日から3年以内に遺産分割ができない場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しましょう。その申請に対して所轄税務署長の承認が得られれば、判決確定の日など一定の日の翌日から4ヶ月以内に分割がなされた場合に、これらの特例の適用を受けられます。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」は国税庁ホームページでダウンロードすることが可能です。
参考:[手続名]遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続|国税庁
相続税の未分割申告に関する相談は税理士へ

このページでは、相続税の未分割申告の概要やデメリット、注意点、計算方法などについてお伝えしました。
相続税の未分割申告を行うと、様々な特例・控除・軽減措置を受けることができないのはデメリットとして理解しておく必要があります。しかし、中には後に更正の請求をすることで、納めすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるのも事実です。
未分割申告そのものが非常に煩雑な手続きとなるのはもちろん、他の相続手続きと並行しながら修正申告を行うことは相続人にとって大きな負担となります。また、税金の計算を正しく行うことは素人にとって非常に難しく、ストレスのかかる作業であることはいうまでもありません。
そのため、未分割での申告が避けられない場合、まずは税理士に相談することをおすすめします。未分割申告、修正申告と2回の申告が必要なことから費用が多少かかってしまう一方、配偶者の税額軽減やその他特例を確実に適用できるでしょう。
相続税に特化している数少ない「川口相続税サポートセンター」では、月50件以上の相続相談を受けている実績があります。過去の事例から照らし合わせて提案ができるのが魅力です。相談は無料でできるため、もし不安な点が少しでもある場合は、ぜひこの機会に一度お問い合わせください。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など