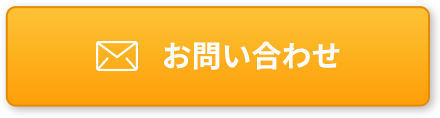相続コラム
相続で不動産を共有名義にするメリットデメリット!トラブルを避けるための対策も

相続する財産に不動産がある場合、誰の名義にするかという問題があります。
特に、実家があっても誰も使わないので空き家にしておいておく場合や、先祖代々で継いできたけども誰も使わない山奥の土地がある場合などには、名義を誰にするか困ってしまうこともあります。
その方法の中に、不動産の名義については共有名義にするということが挙げられます。
このページでは、相続した不動産を共有名義にする場合のメリットやデメリット、またトラブルを避けるための対策についてお伝えします。
不動産の共有名義とは
不動産の共有名義とは、ひとつの不動産を複数人で所有している状態のことを指します。
特に遺言などがなく不動産を相続した場合、遺産分割がされるまで不動産は相続人の共有になるとされています。 一般的には遺産分割によって所有者を決めて相続がなされますが、誰も使わない実家や山奥の土地など、誰の所有(名義)にするか悩んでしまうケースもあるでしょう。
こうした場合に、所有権・登記名義を共有にするケースが見受けられます。相続登記をすると、不動産登記簿に共同相続人全員がそれぞれ合意した持ち分で所有権があることが記載されます。
ひとつの不動産に対して複数の所有者がいるため、それぞれが自分の持ち分に対して所有権を主張可能です。また、不動産を売却する場合には所有者全員の同意を得なければなりません。
相続した不動産の他の分割方法
共有名義とする以外の分割方法として、以下の3つが挙げられます。
- 単独名義とするために現物分割をする
- 単独名義とするために代償分割をする
- 公平を徹底するために換価分割をする
それぞれについて、見ていきましょう。
単独名義とするために現物分割をする
現物分割は不動産を現物のまま、形状や性質を変えずに各相続人に分配する方法のことです。もっともオーソドックスでわかりやすい方法といえます。具体的には「土地は長男、車は長女、預金債権は次女」といった分割方法や、「土地を法定相続分に応じて文筆して分ける」といった方法が挙げられるでしょう。わかりやすい一方で、財産の価値に偏りがある場合には公平性に欠ける相続となりやすい点に注意が必要です。
単独名義とするために代償分割をする
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に金銭等を支払う方法のことです。たとえば、相続人が兄姉の2人の場合、長男が当該不動産を相続する代わりに、妹に対して相続分に見合った現金(代償金)を支払うことになります。代償分割は、相続人全員が納得できる分割が難しい場合に利用されることが少なくありません。
公平を徹底するために換価分割をする
換価分割とは、相続不動産を売却して換金した上で、その代金を相続人で分配する方法のことです。不動産を売却するまでにはさまざまな手続きが必要であるほか、時間もかかりますが、現物分割と比較して公平な分割ができます。また、土地などの財産を売却した場合、相続税以外に譲渡所得などが課税される点に気をつけなければなりません。
相続で不動産を共有名義にするメリット

ここでは、相続した不動産を共有名義にしておくメリットについて確認しましょう。
メリット1:相続人が公平感を持って分割できる
相続した不動産を共有名義にするメリットとして挙げられるのが、遺産分割にあたって相続人が公平感を持って分割できることです。
不動産は形式的には資産ですが、かならずしも歓迎されるものではありません。
実家のような不動産の場合には、お金に変えようにも実家を売却することに他の相続人が反対することが少なくありません。また、固定資産税や設備の維持にお金がかかることから、誰か一人だけが相続するとなると不公平に感じることもあるでしょう。
だれも使わない山奥の土地があるような場合には、微々たるものでも固定資産税がかかりますし、不法投棄をされたような場合には、費用をかける必要が発生し、売ろうにもなかなか売れません。
共有名義にすれば、これらの負担を相続分に応じて承継することになるので、当事者で公平感を持って遺産分割をすることができる可能性が高いでしょう。
メリット2:売却時に控除を受けられる
マイホームを共有名義とした場合に限りますが、売却して利益が出た場合に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できます。この特例は不動産の名義人全員に対して適用されるため、不動産の節税効果が期待できるでしょう。
メリット3:住宅ローンを組む際に有利になる
不動産を共有名義として住宅ローン契約を結ぶと、ローン契約者それぞれの収入を合算したうえでローン審査に臨めます。そのため、単独で住宅ローンを組むより高額なローンを借りられるでしょう。
相続で不動産を共有名義にするデメリット
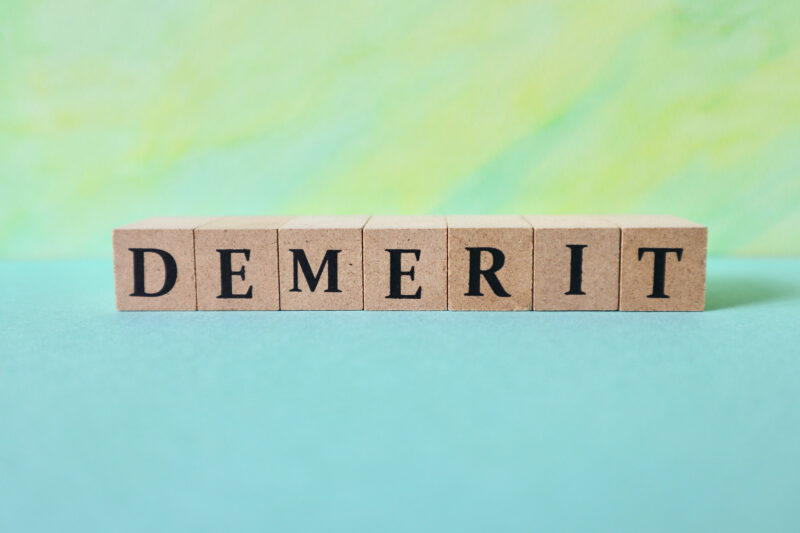
不動産を共有名義にすることで得られるメリットがある一方、デメリットもあります。デメリットについても、みていきましょう。
デメリット1:手続きに相続人全員の同意が必要な場合がある
不動産を共有名義とした場合、相続人全員の同意が揃わずに手続きが困難となることが挙げられます。
物を共有にした場合、保存行為と呼ばれる物の価値を維持する行為は単独でできる一方、売却のような行為については全員の同意が必要です。
実家のような場合に、兄弟の一人が売却に反対するケースはめずらしく、そのような場合には売却ができなくなってしまいます。
デメリット2:持分が細分化されてしまう
利用されない不動産を共有にした場合、相続が起こる度に持ち分がどんどん細分化されることになります。
たとえば、被相続人に子が3人いて、不動産を共有名義にしたとしましょう。
その子にそれぞれ2人づつ子がいた場合、孫の世代になると相続人が6人となります。
共有持分が細分化されればされるほど、手続きが複雑になってしまい、余計に売却などが難しくなってしまうでしょう。
デメリット3:登記をし直す必要がある
一度、共有名義で登記をした後に単独の所有にする場合には、登記をしなおさなければなりません。
不動産の登記には、登録免許税や司法書士への依頼のための費用がかかります。
一度遺産分割をしてから単独所有の名義にするのであれば、その登記は通常の不動産の売買と同じ扱いになるので、登録免許税は相続登記よりも高額です。(相続の場合には固定資産評価額の4/1000ですが、譲渡の場合には20/1000です)
一度共有名義で相続の登記をしたあと、単独の所有に変えようとすると不動産登記費用が多くかかることになります。
デメリット4:トラブルが発生しやすい
不動産を共有にすることで、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 売却するかどうかを巡ってトラブルとなる
- 固定資産税や不動産管理のための費用を巡ってトラブルとなる
- 特定の相続人のみが不動産をずっと使っているなどでトラブルとなる
- 不動産をどのように管理するかでトラブルとなる
- 持ち分の売却をしたような場合には、持ち分を買い取って所有者となった会社との間でトラブルとなる
不動産を共有名義にする場合、これらのトラブルが起こる恐れがあることを理解した上で手続きを進めることが大切です。
デメリット5:売却がしにくくなる
共有の不動産は売却がしにくいといったデメリットがあります。
不動産を購入する際には、現在の権利関係がどのようになっているか、不動産登記簿で確認して不動産会社と交渉をするのが一般的です。
ケースによっては購入希望者が不動産登記簿で共有名義になっていることを理由に購入を躊躇することも考えられ、売却がしにくくなる可能性があります。
共有名義でのトラブルを避けるための対策

共有名義にはどのような対策をするのが良いでしょうか。ここでは、トラブルを避けるための対策を5つ、紹介します。
- 生前に家族で話し合いをする
- 生前に処分をしてしまう
- 遺言で所有者を指定しておく
- 遺産分割協議で不動産についてきちんと話し合う
- 共有名義から抜けたい場合には共有持分のみを買い取る会社に相談
生前に家族で話し合いをする
生前に遺産の話をすることは「縁起でもない」と避けられがちですが、トラブルを避けるためにもきちんと話し合いをしておくことが欠かせません。
特に、不動産に対してあまり知識のない相続人がいる場合と、不動産の相続方法や相続後の扱いについて不公平感が出ることが想定されます。
そのため、不動産を所有することでどのようなメリット・デメリットがあるのかをきちんと相続人間で共有することが大切です。特に、どのような税金・コストがかかっているのかなどについては、トラブルを避けるためにもきちんと確認しておくようにしましょう。
生前に処分をしてしまう
トラブルを避けるために、生前に不動産を処分してしまうのも一つの手でしょう。
たとえば、自宅を所有していても子がそれぞれ独立していて死後に自宅を使う予定がない場合、子としても自宅を売却するという決断をしづらく、共有名義になってしまうケースが多く見受けられます。。
このような場合、住宅については生前に売却をするなどして処分することを検討してもよいでしょう。
昨今ではリバースモーゲージ(自宅を担保にした融資制度のこと)に供して老後資金とすることで、豊かな生活を送るための一助としているケースもあります。
遺言で所有者を指定しておく
これから自分の相続についての対策をするのであれば、不動産の所有者を誰にするかについて遺言で指定しておくことを検討しましょう。
ただし、遺言で所有者とされる人が不動産を単独所有とされることを嫌がる恐れがあるほか、不動産の価値次第では遺留分侵害額請求の対象となることに注意が必要です。
まず、不動産の単独所有をいやがる原因として、主に以下の2点が挙げられます。
- 不動産よりも自由に使える金銭を相続したい
- 不動産の管理や固定資産税などの費用の支払いが面倒だ
そのため、不動産の相続と同時に金銭を相続させるほか、生命保険金の受取人に指定するなどして、自由に使える金銭も用意することも検討しましょう。
ただ、他の相続人から「不動産もお金も相続をして不公平である」という指摘を受ける可能性が否定できないため、不動産の管理にかかる手間や費用について、エンディングノートや遺言の附言事項として付け加えることも有効です。
遺産分割協議で不動産についてきちんと話し合う
被相続人が亡くなった後に不動産の相続が生じた場合、遺産分割協議できちんと話し合い、詳細まできちんと決めるようにしましょう。
遺産分割で共有名義となる不動産については、誰も単独で所有したがらないことが多く、結果として一度共有扱いとなるケースが少なくありません。
また、この際に後の費用負担や利用方法などを決めていないことで、トラブルになることがあります。
民法では、共有物について費用負担についてのルールを規定していますが、あくまでも最低限のルールであることから個々の事情に応じたトラブル回避には役立たないことがあります。
そのため、費用負担や利用ルールについて定めた上で共有名義とするようにしましょう。
共有名義から抜けたい場合には共有持分のみを買い取る会社に相談
共有名義にしてしまったものの、後に費用負担や利用方法についてトラブルになってしまうことも少なくありません。
他の共有者と協議を重ねてもトラブルが解消しない場合、不動産会社の中には共有持分を買い取る会社もあるため、一度相談するのも一つの手でしょう。
相続に関する相談は税理士へ
このページでは相続した不動産を共有名義にすることについてお伝えしました。
相続した不動産の名義について、相続人の公平感を優先した際に利用される共有名義ですが、後にトラブルになることも多いといえます。
分割しづらい不動産がある場合には、まずは専門家に相談してみましょう。
相続や相続税に特化している数少ない「川口相続税サポートセンター」では、月50件以上の相談を受けている実績があります。過去の事例から照らし合わせて提案ができるのが魅力です。相談は無料でできるため、もし不安な点が少しでもある場合は、この機会にぜひ一度お問い合わせください。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など