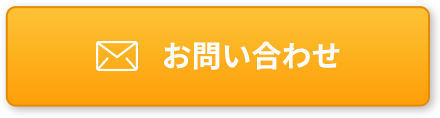相続コラム
相続税における未成年者控除の条件とは?計算方法や手続きも解説

相続をするにあたり、基礎控除額を超える相続税が発生する場合には相続税申告が必要です。申告をする際に手続きを行うことで、控除を受けられるケースがあります。
その中のひとつの「未成年者控除」は、相続人が未成年に限り受けられる制度です。
このページでは、相続税の未成年者控除の内容と、計算方法、手続き面での注意点についてお伝えします。
相続税の未成年者控除とは
相続税における「未成年者控除」とは、相続人が未成年者の場合に本来納めるべき相続税の額から一定額を差し引く制度のことです。
相続をする場合、たとえ相手が未成年者であっても、受け取る際には相続税を納めなくてはなりません。とはいえ、未成年者が相続人である場合、成人になるまでに多くの教育費や養育費が必要です。そこで、未成年者が成人するまでの税負担を軽減する目的として、相続税を軽減する未成年控除の措置が認められています。
相続税の未成年者控除の計算方法
未成年者控除の控除額の計算方法は、以下の通りです。
|
(18歳 ー 相続開始の年齢)✕10万円 |
※年齢は満年齢で計算する
※民法改正によって成人年齢が引き下げられたため、従来の20歳ではなく18歳で計算する
たとえば相続人が14歳11ヶ月の場合、1年未満の端数は切り捨てになるため、相続開始の年齢は14歳で計算します。従って、計算方法は次のようになります。
18歳-14歳(端数切り捨て)✕10万円=60万円
よって、この60万円が相続税額から差し引かれることになります。納める相続税額が50万円であれば、未成年控除額が60万であり、納税額は0円となるでしょう。
また、ここで未成年者控除前の相続税額より未成年者控除額の方が大きい場合、控除しきれない文を未成年者の扶養義務者から控除可能です。
扶養義務者の定義は下記の通りです。
|
相続税法基本通達 1の2-1 相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。 なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正) (出典:国税庁公式サイト) |
つまり、直系血族(祖父母や父母、子、孫)、兄弟姉妹、夫婦は扶養義務者となります。また、上記以外の三親等内の親族については家庭裁判所が特別の事情があると判断した場合に限って、扶養義務が生じることになるでしょう。
相続税の未成年者控除の条件
相続税の未成年控除を受ける場合、次の4つの条件を満たさなくてはなりません。それぞれ見ていきましょう。
日本国内に住所があること
相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所があることが条件となります。そのため、海外に住所がある場合は未成年控除を受けられません。ただし、日本国内に住所がない場合でも、以下の3つのケースでは相続税の未成年控除を受けられます。
|
・日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある ・日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していない場合は、被相続人が、外国人被相続人又は非居住被相続人でないこと ・日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合ではないこと |
財産を取得したときに18歳未満(未成年者)であること
相続や遺贈で財産を取得したときの年齢が、18歳未満であることも条件のひとつです。
また、相続においては、まだ生まれていない胎児も対象者として認められています。そのため、胎児の場合でも未成年者として取り扱い、未成年者控除の適用を受けられることになります。
財産を取得する未成年者が法定相続人であること
未成年者控除を受けるためには、相続や遺贈で財産を取得する未成年者が法定相続人でなくてはなりません。未成年者控除は、親が死亡した場合の相続人である未成年者の生活・養育のための費用を確保するために考慮された制度です。
そのため、法定相続人ではない場合には、未成年控除の対象とはなりません。
取得した財産は相続または遺贈によるものであること
取得した財産が相続又は遺贈によるものであることも条件となります。というのも、未成年者である相続人が1円も取得していない場合、未成年控除を受けることはできません。
とはいえ、相続については相続放棄しているものの、生命保険金の受け取りになっている場合は、相続税の申告をする必要があります。この場合、みなし相続財産となり、未成年者控除を受けることが可能です。
未成年者控除を利用する際の遺産分割協議の流れ
相続人に未成年がいる場合には、一般的な遺産分割の流れと異なる点があります。次の4つの流れに沿って手続きをおこないましょう。
遺産分割協議を行うために特別代理人を選任が必要
未成年控除を受ける場合、未成年では法律行為をおこなうことができません。そのため、特別代理人を選任して、相続の手続きを行う必要があります。
特別代理人には誰を選任するのか
特別代理人には、法律上誰を選ばなければならないという規定はありません。
遺産分割協議案の提出書面から、未成年者を適切に保護できると判断された候補者が選ばれます。候補者には、親族以外にも弁護士や税理士などの専門家が選ばれることがあります。
特別代理人を選任する方法
特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをおこないます。
管轄の裁判所は、「裁判所の管轄区域|裁判所ホームページ」で調べることができるので、確認しておきましょう。なお、申立をおこなう際は、下記の書類が必要です。
|
・申立書 ・未成年者の戸籍謄本 ・親権者または未成年者後見人の戸籍謄本 ・特別代理人の候補者の住民票 ・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案) |
申立書は、こちらでダウンロードが可能です。
申立書を入手できたら、申立手数料800円分の収入印紙を購入し、貼り付けて提出しましょう。また、予納郵券という切手のセットが必要になるので、申立をする管轄の家庭裁判所に問い合わせをして揃えておくことをおすすめします。
手続きには1〜3ヶ月程度の期間がかかるので、相続税申告が必要な場合には早めに準備しておきましょう。
特別代理人と法定相続人で遺産分割をおこなう
特別代理人と法定相続人で遺産分割をおこなう際に、協議の話し合いがまとまった場合には遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がまとまらない場合は、調停・審判によって確定します。
相続税申告をおこなう
相続税申告をする際は10か月以内におこなうようにしましょう。というのも、10か月を過ぎてしまうと、ペナルティが課される恐れがあるためです。速やかに遺産分割協議をおこなうことが大切です。
相続税の未成年者控除の注意点
相続税の未成年控除を受ける場合、以下の3つに注意が必要です。
|
1.遺産分割時に法定代理人の代わりに特別代理人の選任が必要な場合がある 2.相続放棄時の対処方法 3.婚姻した未成年も未成年者控除を使うことができる |
ひとつひとつ見ていきましょう。
遺産分割時に法定代理人の代わりに特別代理人の選任が必要な場合がある
相続税の申告をするためには、前提として遺産分割協議をする必要があります。
未成年者はまだ判断力が十分ではないため、法律行為を単独でおこなえません。そのため、親権者・未成年後見人など法定代理人の同意を得るか、代理してもらう必要があります。
たとえば、父が亡くなって母と子が相続人であり、子が未成年者の場合、親権を喪失しているような事情が無い限り母はまだ親権者として法定代理人です。
しかし、遺産分割協議をする場合、母親は自分自身と子どもの代理人として両方の利益を考慮する必要があるでしょう。母が子の利益を考えずに自分に遺産が遺産全額を取得するような可能性もあるわけです。
このような取引において利害が対立するような状態のことを「利益相反取引」と呼びます。利益相反取引をする際には、未成年者の同意権・代理権を行使するために、裁判所に申立をして、特別代理人の選任をする必要があるでしょう。
次のような場合には利益相反とならないので、特別代理人の選任をする必要はありません。
|
・親権者である母が相続放棄をした(子だけが相続人になるので利益が対立しない) ・普通養子をした場合で実方の相続をする場合(親権者である養方の親は実方の相続人にはならない) |
利益相反をしているかについては、判断が難しいので、是非相続に詳しい税理士に相談をしてみてください。
相続放棄時の対処方法
相続放棄をすると、相続人としての地位を失うため、相続税を支払う必要がなくなります。当然ですが未成年者控除も適用されません。
とはいえ、相続放棄をしても生命保険金を受け取った場合、みなし相続財産を受け取ったことになり、相続税を支払う義務が生じます。その際は、相続人として未成年者控除の適用を受けることが可能なため、手続きの際は忘れずに申請するようにしましょう。
婚姻した未成年も未成年者控除を使うことができる
未成年者は婚姻すると「成年擬制」という制度によって、成年として取り扱われる制度があります。
ただし、これは親の同意や代理人なしで契約を結んだ場合でも、法律上の効力に関する規定に過ぎません。つまり、相続税の申告において、婚姻していても未成年者控除を受けることができます(平17課資2-4改正)。
相続税の未成年控除の相談は税理士へ
このページでは、相続税の未成年者控除について中心にお伝えしました。未成年者の保護の観点から、税制で優遇される制度なのですが、要件の中で把握すべき事項が非常に多いため注意が必要です。
また、相続税申告の前提となる遺産分割協議にあたって、特別代理人を選任する必要がある場合が多く、手続きが複雑でいつもより時間がかかる恐れがあります。
早めに税理士に相談して、テンポよく手続きを行なうようにしましょう。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など