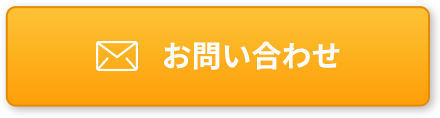相続コラム
貸家建付地の相続税評価額の計算方法をわかりやすく解説!節税のポイントも
不動産を多数所有している方の中には、建物を自分の名義で建築し、賃貸物件として利用していることがあります。このような賃貸物件のための土地のことを相続税法との関係では「貸家建付地」といい、相続税申告の際にその土地をどのように評価するか、どのように評価するかを知った上でどう相続税対策に活かすか、ということが問題になります。
このページでは、貸家建付地の要件や、計算方法、節税対策でのポイント・注意点などをわかりやすくお伝えします。
貸家建付地とは
「貸家建付地」とは、相続税の評価基準で、「貸家(賃貸目的の家屋)の敷地として使われている土地」のことです。たとえば、土地所有者が共同住宅を建てて賃貸している場合、その土地が貸家建付地になります。このような土地は所有者が自由に使えないため、通常の土地(自由地)よりも低い評価額とされるのが一般的です。実際に、財産評価基本通達26では、「貸家建付地」というカテゴリーが設定されているほか、計算方法も「自由地」とは明確に異なっています。
貸家建付地の要件
貸家建付地とするための要件は、以下のふたつです。
- ・土地の上に土地所有者名義の建物があること
- ・建物が賃貸されており、賃料が世間相場並みであること
上記に該当しない場合は、貸宅地をはじめとした別な種別に分類され、今後の取り扱い方が変わる恐れがあります。要件を満たしているかどうか、必ず事前に確認するようにしましょう。
土地の上に土地所有者名義の建物があること
第三者に建物を建築させる目的で「土地」を賃貸する「貸宅地」とは異なり、貸家建付地は、土地所有者が自ら建物を建築し、賃貸することが条件です。建物に第三者が居住することにより、自由に土地を動かせなくなることを考慮した減価といえるでしょう。
賃料が世間相場並みであること
貸家建付地として認められるためには、賃料が世間相場並みであることも必要です。
その理由として、貸家建付地は賃貸に出して他人に使用させることで自用地よりも評価を下げていることが挙げられます。よって、賃料が極めて低いような場合には、実質的には賃貸ではなく使用貸借であると指摘されても言い逃れができないでしょう。
法律上、使用貸借の場合にはすぐに契約を解除して建物を撤去してもらうことが可能です。そのため、使用が制限されているとはいえません。こうしたことから、賃料が極めて低いような場合で、かつ使用貸借と評価できるようなケースにおいて、貸家建付地とは認める必要がないといえるでしょう。貸家建付地としての評価減を認めてもらうためにも、世間相場並みの賃料を受け取って賃貸借であるとみなされる状態にしておくことが大切です。
貸宅地との違い
貸家建付地と混同されやすいものとして、「貸宅地(かしたくち)」が挙げられます。両者は不動産を分類する上で以下のように大きな違いがあります。
- ・貸家建付地:すでに建物が建っている土地で、建物を借りることができる。(借り手は建物のみ使用権を有し、土地の所有権は有しない)
- ・貸宅地:土地そのものを借りられる土地のことを指す。(借り手は土地の使用権を得られるが、建物は自分で建てる必要がある。また土地の所有権も有しない)
つまり、貸家建付地は建物を借りることができる土地、貸宅地は土地そのものを借りることができる土地のことです。なお、貸宅地は貸家建付地と比較して評価額が低く見積もられる傾向にあります。評価額は「自用地評価額×(1-借地権の割合)」といった計算式によって算出可能です。
不動産を借りる際には、自分が何を借りたいのかを明確にし、その条件に合った不動産を選ぶようにしましょう。
貸家建付地の相続税評価額の計算方法
ここでは貸家建付地の相続税評価額の計算方法について見ていきましょう。
貸家建付地の相続税評価額は、「自用地とした場合の相続税評価額-自用地とした場合の相続税評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」といった計算式で求められます。
自用地評価額
自用地評価額とは、貸家建付地を自分で使用するために購入した場合における、その土地の市場価値を指します。つまり、建物がなくとも、その土地自体の価値を評価することになるでしょう。
また、自用地の評価額は土地が存在する場所によって「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかによって計算します。路線価方式は、鉄道路線に近い土地の評価に適している方法です。一方、倍率方式は、周辺の不動産価格に基づいて評価するため、その土地が所在する地域の不動産市場の動向を反映しやすく、評価の信頼性が高い方法とされています。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
路線価方式
路線価方式は、土地の価値を鉄道路線の近さで評価する方法です。つまり、鉄道路線から近いほど土地の価値が高くなるという考え方を指します。路線価方式の計算式は以下の通りです。
路線価方式:相続税路線価×各種補正率×面積
このうち、相続税路線価については路線価図という地図で確認可能です。気になる方は、国税庁のホームページ「路線価図・評価倍率表」で調べることができるので、あわせて参考にしてください。
また、各種補正率とは土地の形状によって評価を調整する乗率のことを指します。こちらの国税庁のウェブサイトで確認可能です。
倍率方式
倍率方式は、周辺の不動産取引価格から不動産の価値を推定する方法です。つまり、周囲の不動産価格が高ければ、その不動産の価値も高くなるという考え方です。倍率方式の計算式は以下の通りです。
倍率方式:固定資産税評価額×倍率
固定資産税評価額は、毎年市区町村役所から送付される「納税通知書」で確認可能です。なお、相続税評価で使用する評価額は被相続人が亡くなった年の分であることに注意しましょう。倍率については先ほどの「路線価図・評価倍率表」に記載があります。
借地権割合
借地権割合とは、賃貸借によって土地を借りて建物を保有している場合の、借地権の評価をするための割合です。借地権割合は、土地によって30%~90%の間で定められています。借地権割合は上述の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に記載があります。
路線価地域の場合には路線価とともにアルファベットが書かれており、アルファベットに応じた借地権割合が以下のように設定されています。
A=90%
B=80%
C=70%
D=60%
E=50%
F=40%
G=30%
たとえば、「100B」と記載されている場合には、路線価は1平方メートルあたり10万円(100千円)で、借地権割合は80%となります。なお、アルファベットがない地域は20%となります。
倍率方式については評価倍率の表に記載がありますので、それに従います。 「−」となっているものについては20%で計算します。この割合は、人通りが多く商業的な利用価値が高い都会のほうが高い傾向にあります。
借家権割合
借家権割合とは、建物を賃貸しているときに、相続税の計算をするために用いられる割合のことです。借家権割合は、2023年現在、全国のどの地域であっても一律30%とされています。
借家権割合を調べる際は、「路線価図・評価倍率表」にて確認可能です。借家権割合を調べたい都道府県をクリックした後、「借家権割合」の文言をクリックすることで割合がわかります。
賃貸割合
賃貸割合は、実際に賃貸されている部分を計算するための割合のことです。賃貸割合は賃貸されている部屋の戸数で考えるのではなく、賃貸されている床面積によって考えます。そのため、5室あるうち4室が賃貸されている場合でも、4/5と計算されるわけではなく、4室の床面積/5室の床面積で計算しなければなりません。
参考:国税庁|貸家建付地の評価
節税対策で貸家建付地を検討する際のポイント・注意点
ここでは、節税対策で貸家建付地を検討する際のポイントおよび注意点について紹介します。
- 1自用地として持っているよりも貸家建付地の方が評価額は下がる
- 2賃貸併用住宅を建てた場合
- 3貸し駐車場と貸家建付地の関係性
- 4空室の判断について
- 5数棟の貸家がある場合の評価方法
ひとつずつ、見ていきましょう。
自用地として持っているよりも貸家建付地の方が評価額は下がる
貸家建付地は自用地として持っているよりも評価額が下がる点に注意が必要です。具体例として、ここでは以下のような条件を満たした土地があると仮定しましょう。
- 自用地評価額5,000万円
- 借地権60%
- 建物の賃貸状況は100㎡中100㎡は貸し付けられている(=満室)
この土地を貸家建付地として評価した場合、次のようになります。
5,000万円 ー(5,000万円 × 60% × 30% × 100㎡/100㎡)=4,100万円
計算式から分かるように、借地権割合が60%の地域で賃貸割合が100%であれば、評価額は4,100万円となります。実質、18%の減価が可能となり、自用地として持ち続けているよりも相続税を下げられるでしょう。
また、賃貸をすることにより、賃料として現預金を取得できます。現預金はそのまま生活費として使うことはもちろん、生前贈与をする・そのお金で生命保険を申込むなど、他の相続税対策に利用することも可能です。貸家建付地の利用は直接的にも間接的にも相続税対策に繋がるといえます。
賃貸併用住宅を建てた場合
たとえば、アパート・マンションを建てる際に最上階のみを自分たちで使用し、あとの部分は賃貸に出すといったケースも見受けられます。こうした形態を「賃貸併用住宅」といい、この場合には賃貸されている部分に関してのみ、相続税評価額の減額が可能です。
自宅として利用しているだけの場合には、全てが自用地として計算されます。しかし、賃貸併用住宅とすることで、評価を下げられるでしょう。
貸し駐車場と貸家建付地の関係性
昨今では遊休不動産の活用方法として、貸し駐車場の人気が高まっています。貸し駐車場にする場合、工作物を設置する一方で、建物を建てるわけではありません。そのため、貸し駐車場は貸家建付地の要件を満たすことができず、その土地は貸家建付地とはならない点に注意が必要です。
しかし、アパートやマンションと地続きの土地を所有しており、建物の入居者専用の駐車場として利用している場合はどうでしょうか。このようなケースにおいて、駐車場にも貸家建付地の減価を適用することが認められています。一方、以下のような注意点があるので覚えておきましょう。
- 1台でも建物の入居者以外の人に賃貸している場合、貸家建付地の減価は適用できない
- いくら専用駐車場だとしても、建物と駐車場との間に道路があり、物理的に分断されているような駐車場も貸家建付地の減価は適用できない
つまり、あくまで建物と一体利用されていて切り離せないものだという事実が必要ということです。
空室の判断について
賃貸割合は実際に賃貸している床面積の合計で計算します。つまり、空室が少ない方が賃貸割合が上がるため、土地の評価額を下げる効果は高くなるでしょう。
また、空室かどうかは相続発生時点で判断するため、そのときに空室になっているときには、空室分は賃貸割合に含めないのが原則です。
しかし、たとえば学生の入居希望者が目立つアパートを所有している場合において、3月に入居している人の多くが退去するものの、4月にはまた新たな学生が入居するということがあります。
そこで、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分がある場合」には、以下のような事情を総合的に考慮して計算を認めるかどうかが決まります。
- 空室となっている部分が継続的に賃貸されているか
- 前の賃貸人が退去した後にすみやかに募集をかけているか
- 空室となっている間にほかの利用方法がされていないか
- 空室期間が1ヶ月ほどの限られた期間であること
- 課税時期後の賃貸が一時的なものではないか
数棟の貸家がある場合の評価方法
一つの土地に複数の貸家がある場合も、評価の方法が変化します。この場合、貸家の数分だけ画地を分けて個別に評価するのが原則です。たとえばアパートが2棟ある場合、2画地として計算します。
また、敷地を区分する必要がある場合、正確な値を求めるために測量が実施されることもあるでしょう。このように、評価単位を分けるのは難しい判断をすることが多く、複雑な計算が必要となるケースも少なくありません。素人判断に頼るのではなく、早めに税理士等の専門家に相談することでトラブルを未然に防げるでしょう。
貸家建付地の評価額の計算方法をチェック
このページでは「貸家建付地」をテーマに要件や計算方法、節税対策のポイント・注意点などをわかりやすく解説しました。
土地がある場合の評価の方法として複雑な計算を要求されるものですが、うまく利用すれば相続税の評価額を下げる効果があります。
ぜひこの機会に税理士に相談し、賢い相続税対策を始めましょう。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など