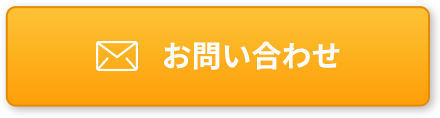相続コラム
家庭用財産の相続税評価における原則と例外!種類別の解説も

家具、家電、衣類など家庭用財産の相続税評価方法について解説します。
不動産に比べると評価方法そのものは複雑ではありません。
しかし骨董品の存在や自動車の扱いなど、知らなくてあとで痛い目にあうケースもありますので注意が必要です。
財産の種類ごとに相続税評価方法の特徴を説明していますのでぜひ参考にしてみてください。
相続税の家庭用財産とは?
相続税における「家庭用財産」とは、家庭にある一般動産のことを指します。家具や自動車、骨董品や貴金属、時計などが該当するでしょう。
わかりやすくいえば、家庭用財産とは不動産、現金・預貯金、保険金、有価証券のどれにも属さない「その他の財産」だといえます。
家庭用財産の評価単位とは
原則として、相続財産の計算は被相続人の財産をひとつずつ評価し、相続税申告書に記入しなければなりません。しかし、家庭用財産に該当する動産は非常に数が多いうえ、それぞれを明確に評価することが困難でしょうそのため、実際の申告において家財用財産は「家財道具一式30万円」といった具合に、一つの財産としてまとめて扱われるケースがほとんどです。
一方で、自動車や一骨董品、貴金属など、動産であっても一定の価値があると税務署が考えた財産については個別に申告しなければなりません。ここで一度、「財産評価基本通達」を元に家庭用財産の扱いを確認してみましょう。
財産評価基本通達では、相続財産の評価方法が財産の種類ごとに規定されているほか、以下のように評価すべきだと言及されています。
|
財産評価基本通達128 動産(中略)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。 ただし、家庭用動産(中略)で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して(中略)評価することができる 引用元:国税庁 |
通達で述べられている内容を要約すると、「5万円の価値を超えるものは一つの財産としてカウントしましょう。」といった意味になるでしょう。逆にいえば、5万円以下のものはまとめて一つの財産としてカウントして問題ありません。
原則
通達によると、家庭用財産は原則として1個または1組ごとに評価しなければなりません。ただし、原則が適用されるのは5万円を超える財産のみに限られています。
たとえば冷蔵庫やエアコン、パソコン、スマートフォンなど、ものによっては5万円を超える財産もあるでしょう。その場合は、「ノートパソコン-9万円」、「エアコン-7万円」のように個別に申告する必要があります。
また、ここで記入する金額は新品価格ではなく中古品を購入すると想定した場合の金額であることに注意が必要です。そのため、一部を除き、一般の家庭では5万円超の価値がある財産はごく一部に限られるでしょう。
例外
5万円以下の財産はまとめて一つの財産として扱います。
食器や書籍、衣類など5万円以下のものとなるとあらゆるものが含まれますが、それらをまとめて「家財一式30万円」などと評価して申告可能です。
相続した家庭用財産の評価方法
家庭用財産の評価方法については、「財産評価基本通達」で以下のように言及されています。
|
財産評価基本通達129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。 ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売 価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する 引用元:国税庁 |
通達より、家庭用財産は原則として「売買実例価額」あるいは「精通者意見価格」で評価する必要があります。とはいえ、家庭用財産の中には正確な相場価格を算出することが難しいものも含まれており、こうした財産については例外として「相続開始時の未償却残高」で評価することが認められていると判断できるでしょう。
|
【家庭用財産の評価方法】 ✔ 相続開始後に売却した場合、「売買実例価額」として計上する ✔ 売却していない場合には「精通者意見価格等(いわゆる買取業者の査定価格)」で計上する ✔ 上記をもってしても買取価格が判明しない場合、「相続開始時の未償却残高」で計上する |
【原則】売買実例価額ならびに精通者意見価格等を参考に計上する
家庭用財産の場合、類似の財産の売買実例価額を基準とし、精通者意見価格等を考慮して評価額を求めるのが原則です。なお、「売買実例価額」と「精通者意見価格」はそれぞれ次の価格のことを指します。
|
・売買実例価額:実際に売買される価額のこと ・精通者意見価額:買取業者等に査定してもらい算出される価額のこと |
家庭用財産はもともと、「評価価額に相当する金額」で評価するものだと定められていました。しかし、平成20年に財産評価基本通達が一部改正されたことにより、評価に対する方針が変わっています。
【例外】相続開始時の未償却残高で計上する
上記の方法をもってしても、評価額が計上できない場合、例外としてこの算出法が認められています。具体的には以下の算式によって算出します。
|
同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額―製造時から相続開始時までの減価償却費 |
なお、減価償却費については「財産評価基本通達」において次のように定められています。
|
財産評価基本通達130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正) (1) 耐用年数 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。 (2) 償却方法 償却方法は、定率法による。 引用元:国税庁 |
とはいえ、減価償却の求め方は複雑なため、税理士等の専門家に頼んで算出してもらうことをおすすめします。
家庭用財産の相続税評価を種類別に解説
家庭用財産をいくつかの種類に分けて、それぞれの相続税評価のポイントを紹介します。
5万円以上の値がつけば個別に申告するのが原則です。しかし動産は少額におさまる場合がほとんどであることから、一部例外を除いて基本的には家財一式に含まれるでしょう。
ここでは家庭用財産の相続税評価を種類別に解説します。
|
1.自動車
原則として、自動車は一般用動産として評価します。なお、自動車の相続税評価で大切なポイントとして名義に惑わされないように注意しましょう。自動車の購入にあたって誰の財布からお金が出たかが重要で、名義人は問題ではありません。
亡くなった父親が大学生の息子に自動車を買い与えた場合、名義が息子であっても相続税の視点からは亡き父親の財産とみなされます。その理由として、自動車は父親が自らお金を出して購入した財産だからです。この点は勘違いする人が多いポイントでもあるので注意しましょう。
自動車は一般的に、中古車市場の買い取り価格相場や査定額等をもとに評価額を算出するケースがほとんどです。一度問い合わせてみると良いでしょう。
2.骨董品・美術品
骨董品や美術品は家庭用財産のなかでも特に注意が必要な品目といえるでしょう。
というのもパソコンやテレビなどの家財道具と違って、一部の骨董品や美術品は相場を判断するのが難しく、高値がつく恐れがあるからです。プロによる鑑定の結果、数百万円の価値がついたというケースも珍しくありません。場合によっては購入時よりも大幅に評価額が上がっていることもあるでしょう。そのため、家具や家電と異なり中古だから値段が下がっているだろうというルールは当てはまらないことになります。
遺品整理の際に価値のありそうな骨董品や美術品を発見した場合は、プロに鑑定してもらうのが原則です。裏付けのある鑑定には鑑定費用がかかりますが、ここできちんと鑑定しておかないと後々税務調査で指摘される可能性が否定できません。(※鑑定費用を必要経費として計上することもできない)
鑑定の結果、5万円超の値がつけば個別の申告対象となり、5万円以下であれば家財一式に含めることができます。鑑定時にもらった評価鑑定書は忘れずに保管して置くようにしましょう。
3.貴金属・宝石
ダイヤやパール、金地金等の貴金属が該当します。貴金属も自動車と同様に、原則として「売買実例価額」や「精通者意見価格」を元に評価額を算出するのが一般的です。
ジュエリー専門の買取業者はたくさんあることから、わりと簡単に相場を知ることができるでしょう。査定の結果、5万円を超えるものがあれば個別での申告が必要です。
4.電話加入権
かつて、家の固定電話が主な連絡手段であったころは電話加入権が価値のある財産だとみなされていました。(NTTができた際の電話加入権は72,000円)しかし、2005年3月1日からは携帯電話等の普及もあって、電話加入がそれまでの半額の36,000円に引き下げられています。
また、電話加入権の相続税評価はかつて1回線あたり1,500円と定められていましたが、令和3年に改正されて現在は個別に扱う必要がなくなりました。家財一式に含めることで足ります。
5.家具
タンス、ベッド、本棚など家の中にある家具は一般動産に該当します。そのため、先述した「売買実例価額」または「未償却残高」によって評価することになるでしょう。ただし、新品に近い商品やアンティーク家具は個別の申告対象になる可能性があるため、買取業者に査定してもらうことをおすすめします。
6.家電
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど家電製品の多くは、経年劣化により相続時には価値がなくなってしまっているものがほとんどです。とはいえ、家具同様に新品に近い商品は中古業者に依頼して査定を取ってもらい、相場を把握するのが無難かもしれません。
また、スマートフォンやノートパソコンも商品によっては中古市場で高値で取引される点に注意しましょう。
7.衣服
衣類やカバン、靴などについては基本的に他の動産と一緒に「家財一式」として処理することがほとんどです。ただし、海外の高級ブランドなど一見して明らかに高値で売却できそうなものは、中古買取ショップに査定を依頼して相場を把握することをおすすめします。
8.ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は財産として扱われます。相続税評価額は取引価額の70%です。
税務署の調査では家庭用財産もチェックするの?
税務調査の現場では、税務署員は「こんなものまで?」と疑問に思うようなものまでチェックします。
なかでも骨董品や美術品など素人目線では価値の判断が難しいものについては、税務調査の後に税務署がわざわざ専門家に鑑定を依頼することも少なくありません。
ほかにも自宅にゴルフ大会のトロフィーが飾ってあった場合、トロフィーそのものの価値よりゴルフ会員権の存在を疑われることもあるでしょう。神経質になりすぎる必要もありませんが、税務署が骨董品や美術品の価値を思っている以上に気にする点は、知っておいたほうが無難です。
まとめ
家庭用財産の相続税評価方法と注意点を紹介しました。家庭用財産は少額で価値の低いものがほとんどであり、不動産に比べると評価の方法も簡素です。
しかし、自動車や骨董品のように、思わぬ落とし穴もあることに注意しましょう。
|
上記のポイントを押さえつつ漏れのない相続税申告書を作成しましょう。
最後になりますが、家庭用財産に限らず相続財産の評価方法で迷うことがあれば税理士へ相談することをおすすめします。よくわからないからと適当な申告をしてしまうと、税務調査の対象となる恐れがあります。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など