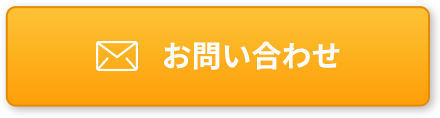相続コラム
相続税の申告期限と納付期限はいつまで?間に合わない時の対応や延長方法
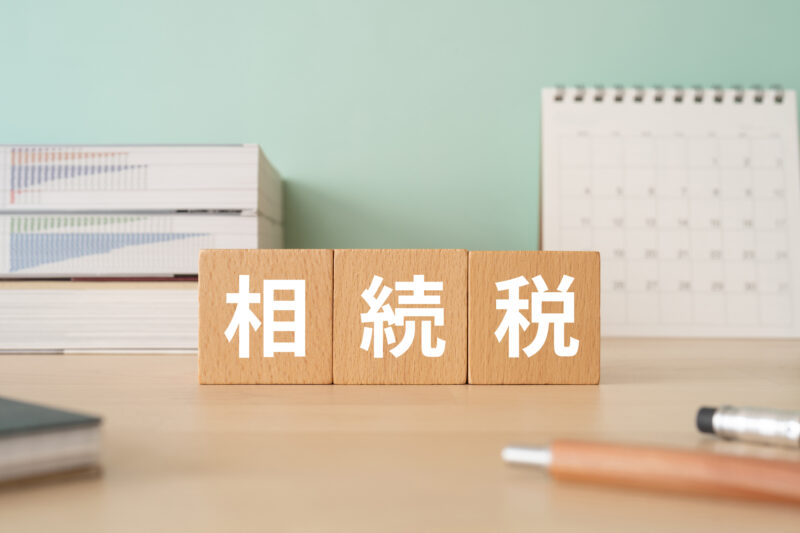
被相続人に多額の相続財産があった場合には相続税申告をする必要があります。
なんとなく、相続税は10ヶ月以内と覚えていても、申告なのか納付なのか、例外的に10ヶ月を越えて納税することはできるのか、間に合わない場合に延長ができるのか、詳しいことまでは知らないという方も多いのではないでしょうか。
このページでは、相続税の申告期限と納付期限はいつまでなのか、また例外や間に合わない時の対応や延長方法についてみていきます。
相続税の申告期限と納付期限はいつまで?
それでは早速、相続税の申告期限と納付期限はいつまでなのかをみていきます。
相続税の申告および納付期限は相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内です。
ここでのポイントとして、以下の2点が挙げられます。
|
・申告・納付ともに10ヶ月以内に行うこと ・10ヶ月の期間制限は相続開始があったことを知った日の翌日から計算する |
この記事を読んでいる方の中には、「相続税の申告・納付期限が10ヶ月もあるなら、そんなに急がなくたって大丈夫でしょう?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、相続手続きは法定相続人の間で話し合いがスムーズに進まないケースが多く見受けられるほか、手続きそのものも非常に煩雑です。そのため、相続が発生したことが分かった時点でなるべく速やかに手続きを進めるようにしましょう。
被相続人が死亡した日
先ほど、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を済ませる必要があるとお伝えしました。とはいえ、ここでいう「被相続人が死亡した日」は状況によって必ずしも死亡届が提出された日になるとは限りません。
被相続人が死亡したとみなされる日には、以下のケースが挙げられます。
|
・死亡届が提出された場合には、死亡届に記載された日時 ・普通失踪(民法30条1項)による失踪宣告があった日には7年の期間満了時 ・特別失踪(民法30条2項)による失踪宣告があった場合には危難が去った日 ・認定死亡(戸籍法89条)がされた場合には死亡したと認定された日 |
一般的には死亡届が出された日を死亡した日となりますが、上記のような特殊なケースがあることも頭の片隅においておくようにしましょう。
10ヶ月という期間は長い?短い?
相続や人の死亡に関する手続きは多岐にわたり、それぞれに期限が設けられています。個々では被相続人が死亡した後、1年以内に行わなければならない主な手続きについて下表にまとめてみました。
|
期限 |
手続き項目 |
|
7日・14日以内 |
・死亡届の提出 ・火葬許可申請書の提出 ・年金の受給停止 ・健康保険の資格喪失 ・世帯主の変更 ・公共料金の名義変更 |
|
3ヶ月・4ヶ月以内 |
・相続放棄・限定承認 ・準確定申告 |
|
10ヶ月・1年以内 |
・相続税の申告・納付 ・遺留分侵害請求 |
「思っていたよりもやることが多い」と感じたのではないでしょうか。相続税の申告までに遺産分割協議を終えておく必要があるほか、相続の仕方についても法定相続人がそれぞれ決めなければなりません。
そのため、10ヶ月は決して長い期間ではなく、場合によっては期限ギリギリまで慌ただしい日々が続くこともあるでしょう。限られた期間の中でさまざまな手続きを済ませる必要があり、期限に間に合わないということを防ぐために進捗状況を確認しながら着実に進めていくことが大切です。
相続税申告の起算日が問題になるケース
以上の原則から、相続税申告の起算日が問題になる場合を確認しましょう。
|
相続開始日を知らなかった場合
「被相続人が死亡した日」が「相続人が死亡した日を知った日」は基本的に同日となりますが、中にはそうならないケースもあるでしょう。(例:兄弟間が不仲で遠方に住む両親の死をすぐに教えてもらえなかった等)
その場合、一部の相続人は被相続人が亡くなったことを知るタイミングが他の相続人よりも遅れてしまいます。このような場合において、死亡を知らされていなかった相続人の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月後となる点に注意しましょう。
|
死亡日 |
死亡を知った日 |
実際の申告期限 |
|
2月10日 |
5月15日 |
翌年3月15日 |
なお、申告書に相続開始を知った日を記載する欄がありますが、念の為相続開始を知った日についての記録(例:相続人から通知を受けたときの通知など)を残しておくようにしましょう。
二次相続が発生した場合
二次相続とは、被相続人の配偶者が亡くなり、被相続人から配偶者へ相続された相続分を配偶者の相続人が相続することです。
一次相続と比較すると、以下のようになります。
|
一次相続:夫が亡くなり、妻と子が相続人となる 二次相続:夫が亡くなった後に妻も亡くなってしまい、子が相続人となる |
実際に、下記のような相続が発生したと仮定しましょう。
|
という相続があったとします。
このときに、子Cが亡くなって妻E・Fが相続をすることになりますが、Aが亡くなったことによって相続税申告が必要となった分については、Cが亡くなったことを知った翌日から起算する点に注意しましょう。
相続人以外への遺贈の場合
遺贈とは、遺言によって遺産を渡すことです。
被相続人以外に遺贈をする際には、遺贈を受けた人は相続税申告をする必要があります。とはいえ、遺言書が見つかって相続人から知らせてもらうまで相続が開始したことを知らないケースもあるでしょう。
|
死亡日 |
死亡を知った日 |
実際の申告期限 |
|
3月15日 |
4月10日 |
翌年2月10日 |
このような場合には、被相続人が亡くなって自分が遺贈を受けていることを知った日から起算します。
相続欠格に該当・推定相続人の廃除がされた場合
法定相続人であっても、相続欠格に該当したり(民法891条)、推定相続人の廃除(民法892条)がされることによって、相続人ではなくなることがあります。
これによって、代襲相続が発生したり(民法887条)、相続の順位が変わることによって、新たに相続人になる人が発生することがあります。
この場合の起算日は、相続が開始して、かつ、相続欠格に該当・推定相続人の廃除がされて自分が相続人になったことを知った翌日です。
申告・納付期限が土日祝日の場合
土・日・祝日、および年末年始(12月29日から翌年1月3日)は税務署がお休みとなります。税務署が休みの場合、これらの日の翌日が期限となる点に注意しましょう。
停止条件付の遺贈によって財産を取得した場合
遺贈をするにあたって、条件を記載することがあります。条件には、ある条件が成立したときに効力が生じる停止条件と、ある条件が成立すると効力を消滅させる解除条件があります。
停止条件は、条件が成立したときに効果が発生するので、条件成立前には遺贈の効果が発生していません。そのため、条件が成立して遺贈の効果が発生した日の翌日が起算日です。
弁識能力がない人または胎児が相続人の場合
相続人が乳幼児、あるいは認知症等で著しく判断能力が低下している場合、自分が相続人であると認識することは困難です。そのような場合、法定代理人を選任した上で相続手続きを進めることになるでしょう。
また、そのケースにおいて相続申告期限は法定相続人がその相続開始を知った日の翌月から10ヶ月以内となります。なお、相続開始時に法定代理人がいないときは後見代理人が選任された日の翌日から10ヶ月以内です。
なお、被相続人が亡くなったときに、被相続人の子が胎児である場合には、例外として権利能力が認められ、相続人になることができます(民法886条)。
この場合は、子が生まれて、親権者である母親が相続開始を知った日の翌日から期限が起算されます。なお、母親も共同相続人になる場合には、特別代理人の選任が必要ですので、特別代理人が相続開始を知った日の翌日から起算する点に注意しましょう。
相続税の申告期限の延長が認められる例外
相続税の申告期限は厳格で、例外として延長が認められるのは自然災害などにより申告が難しい場合が挙げられます。過去には、東日本大震災が発生したときに延長が認められたほか、新型コロナウィルスの感染拡大によっても延長が認められました。
とはいえ、延長が認められるのはかなり特殊なケースに限られるため、基本的に延長が認められる例外はないものと考えておいた方が無難でしょう。
相続税の申告期限・納付期限に間に合わない時の対応
ここでは、相続人の間でのトラブル等により申告・納付期限に間に合わない時の対応について、解説します。
申告期限に間に合わない時の対応
申告期限に間に合わないケースとして、遺産分割協議で言い争いになってしまい、各人の相続分が計算できないなどが挙げられます。このように申告期限に間に合わない場合、一体どういった対応を取れば良いでしょうか。
相続人の間のトラブル等により申告期限に間に合わない場合、いったん法定相続分で分割したものとみなして各人の相続分を計算することになります。そこで求められた仮の相続分を元に申告書(分割見込み書)の作成を行いましょう。
ゆくゆくトラブルが解消し、正しい相続分が明らかになった時点で厚生の請求を行うことで、本来の計算にしたがった相続税の差額を取り戻すことが可能です。
というのも、遺産分割協議が終わっていない場合、小規模宅地等の特例や配偶者控除といった税制優遇の措置を利用することができません。その結果、払いすぎている相続税が多額になるケースが多く見受けられるからです。
なお、更生の請求をすることができるケースについては相続税法32条1項において、以下のように規定されています。
|
・遺産分割が間に合わず一旦相続分の割合で申告をした場合 ・認知の訴え・推定相続人の廃除・相続回復請求権・相続放棄の取消などで相続人に異動が生じた ・遺留分侵害額請求によって支払う額が確定した ・遺言書が発見された・遺贈が放棄された |
また、更生の請求は4ヶ月以内に行なう必要がありますので、こちらも併わせて期限に注意しましょう。
納付期限に間に合わない時の対策
相続税の納付は、納付期限までに一括で金銭にて支払わなければなりません。万が一、納付期限に一括で支払いできない場合、例外として「物納」と「延納」の2つの方法が認められています。物納とは、金銭ではなく相続をした物を納付することによって、金銭の支払いに替えることを指し、延納は本来一括で支払う金額を分割して払っていく方法のことです。
とはいえ、いずれも利用に当たっては一括納付が難しい正当な理由が必要なので注意しましょう。
相続税の申告期限を過ぎてしまうデメリット
相続税の申告・納付の期限に間に合わず、過ぎてしまうと、様々なデメリットがあります。
|
控除・軽減の制度が受けられない
相続税には、税負担を軽くするための控除・軽減の制度がたくさんあります。たとえば、相続税の配偶者控除(税額の軽減)のような制度を利用することで、配偶者は相続税を負担しなくてよい可能性が高まるでしょう。
とはいえ、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、控除・軽減の制度が利用できなくなるケースがあります。代表的なものとして、先に述べた配偶者控除がこれにあたります。
なお、宅地の評価を最大80%下げることができる小規模宅地等の特例については、期限後申告でも適用することができるので安心してください。
無申告加算税
期限内に相続税申告をしなかった場合、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は以下の通りです。
|
本来納付すべき税額の50万円以内の部分:15% 本来納付すべき税額の50万円を超える部分:20% |
重加算税
無申告が悪質であると評価された場合、重加算税として40%が加算されます。
延滞税
令和5年1月1日から12月31日の相続税における延滞税は、以下の通り税率が定められています。
|
納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年2.4% 納期限の翌日から2か月を経過した日以後:年8.7% |
故意の申告書不提出
期限内に申告書を提出せずに相続税を免れた場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が課されます。
無申告犯
正当な理由なく期限内に申告書を提出しなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
税理士に支払う報酬が高くなる可能性
相続税申告を期限後に申告する際、税理士に依頼することで本来よりも税理士報酬が高くなる恐れがあります。これは、税理士が普段よりも急いで申告を行なうためで、期限内でも申告期限まで時間がないような場合には、報酬額が高くなることがほとんどです。
相続税の申告期限と納付期限に要注意
このページでは、相続税の申告期限と納付期限はいつまでなのか、例外はあるのか、間に合わない時はどうするべきなのかなどをお伝えしました。
相続税申告の10ヶ月という期間は長いようであっというまに過ぎてしまい、過ぎるとデメリットやペナルティなどが多数あります。
なるべく早い段階で税理士に相談・依頼することをおすすめします。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など