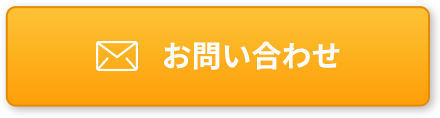相続コラム
相続税申告における手許現金とは?税務署の指摘やペナルティについて
相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合には相続税の申告・納税が必要となります。
相続税申告における手許現金について、申告しなくてもわからないのではないかという疑問を持つ方も多いでしょう。
このページでは、相続税申告において、手許現金をどのように取り扱うべきかについてお伝えします。
手許現金とは
手許現金とは、その名の通り手許(手元)で保有している現金のことです。ここでいう現金とは、相続開始時点で預金口座等に入っていないお金を指します。
手許現金に該当するものとして、次のようなケースが考えられます。
- 1財布の中の現金等
- 2タンス預金や貸金庫においていた現金
- 3相続開始直前引き出し預金
財布の中の現金等
被相続人の財布の中に入っていた現金は当然、手許現金として相続財産になります。中には、財布に数千円程度しか入っていなかった場合に「このぐらいの金額なら黙っていても問題ないだろう」と考える方もいるかもしれません。しかし、原則として故人のお金は1円単位で相続財産とみなされることから注意が必要です。実際に金額の大小問わず故人の現金が残っていたのに、申告しなかった(少なく申告した)ことで税務署からペナルティーが科されたケースも少なくありません。
タンス預金や貸金庫においていた現金
いわゆるタンス預金や貸金庫に置いていた現金も、手許現金の代表といえます。
これらの現金は、いわゆる形見分け・遺品整理と呼ばれる作業で見つかることがほとんどです。また、その際に他の相続人に黙って発見者が着服するケースも多く、タンス預金が元で生じるトラブルは後を絶ちません。遺品整理でタンスや貸金庫の中を確認する場合は複数の相続人で確認する、あるいは立会人を呼ぶといった対策を講じましょう。
相続開始直前引き出し預金
被相続人が亡くなる前に引き出された現金は「相続開始直前引き出し預金」「直前引き出し」などと呼ばれ、手許現金に当てはまります。 一般的に亡くなったことが判明した時点で預金口座は凍結され、正当な手続きを踏まなければ引き出すことができません。
そうした事情を知っている被相続人本人あるいは代理の家族等が、亡くなった後のことを考え被相続人の預金口座からある程度まとまった現金を引きだして保管しておくといった話はよくあることです。
しかし、たとえどんな理由があろうとも相続が開始する直前に引き出された現金は手許現金として扱われ、相続財産の対象となります。
【ケース別】手許現金の対処法
手許現金にどういったお金が該当するのか理解したところで、よくある2つのケースをもとに手許現金の対処法について紹介します。
相続開始日(死亡日)以降に使ってしまったケース
被相続人が亡くなる直前に引き出した現金を相続開始日以降に使ってしまった、というのはよくあるケースのひとつです。用途として、葬儀代やお布施・お車代などの支払いに充当されるといったことが挙げられるでしょう。
たとえば、相続発生後に以下のような状況だったとしたらどうでしょうか。
手許現金から病院への支払い:20万円
手許現金から葬儀代への支払い:80万円
手許現金の残高:50万円
このケースにおいて、計150万円が相続財産として計上されることになります。また、上記のうち葬儀費用は相続財産から控除することが可能ですが、手許現金に計上しなくてよいことにはなりません。被相続人が死亡した時点では、150万円の手許現金があったことに違いはなく、またその事実にともない申告も必要となります。
被相続人の現金と配偶者の現金が混ざっているケース
夫婦間でよくあるケースとして、家計で使うお金を夫婦で分けずに管理しているといったことが挙げられます。その場合に、夫婦のどちらかが亡くなって相続が生じるとどうなるでしょうか。手許現金のうち、被相続人の割合がどの程度なのかわからず、困ってしまいますよね。
たとえば夫婦が同居しているときには、夫婦で一緒の貯金箱に貯金をしていたり、買い物用の財布に夫婦それぞれが現金を補充していたりするとしましょう。どちらがいつ、いくらお金を入れたか、正確に追跡するのは、事実上不可能です。
この場合、少々手間はかかりますが、過去の実績をもとに推定で計算をするしかありません。
たとえば、過去数年間にわたるATMの引き出し額の合計からおおよその割合を出す、クレジットカードの利用明細から月々の使用額を判断するといった具合になるでしょう。
手許現金は法律上は相続人全員の共有となる
手許現金は法律上、相続人全員の共有財産として扱われます。とはいえ、現金は有体物である動産であることから、法定相続分に応じて当然に分割するわけにもいきません。そのため、原則として手許現金の相続割合については遺産分割協議にて決することになります。
現金が外貨である場合の相続税評価について
手許現金は、被相続人が亡くなったときに存在した現金の価額がそのまま評価額となります。一方で、現金が外貨であった場合はどうでしょうか。たとえば、海外に訪れる機会が多いことから、一定額を外貨で保有していたといった例が当てはまります。
このような場合、外貨を邦貨換算して評価額を求める必要があります。
【出典】国税庁|財産評価基本通達4-3
なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。)を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外改正)
上記通達のうち、「課税時期」とは相続において被相続人の死亡した日のことを指します。「対顧客直物電信買相場(TTB)」とは、外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を円に交換する場合に適用される為替相場のことをいいます。
手許現金は税務署にばれるのか?
手許現金は特にどこかに記録されているわけでもなく「現金として使っている以上は誰にもバレないだろう」と考えている方も多いかも知れません。しかし、手許現金は税務署にバレないといった考え方は極めて危険であり、基本的にはバレると考えておいた方がよいでしょう。
ここでは手許現金がなぜ税務署にバレるのか、その理由についてご紹介します。
税務署は10年間の預金の流れを確認する
税務署は個人収入や資産の動きを「国税総合管理システム(KSK)」で把握しています。システムを利用することで個人が得ている収入額はもちろん納税額に至るまで、過去10年に遡って照会可能です。そのため、生前に一定額の収入を得ているにもかかわらず相続税額が少ない場合、「資産をどこかに隠しているのではないか」と疑われても不思議はないでしょう。
また、10年以上前からあるタンス預金等であればバレないのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、たとえ10年以上前であったとしても金額がそれなりに大きい場合、税務署の調査によって追及される恐れがあります。税務調査では家の中を隈なく調べられることはもちろん、被相続人のみならず家族の銀行口座も対象です。そのため、基本的に税務調査を逃れることは困難であると考えましょう。
前提として、納税は国民の義務であり脱税は犯罪となります。ばれなければ犯罪行為をしてもいいということにはならないため、正確な申告を心がけましょう。
海外への送金や海外の資産も調査の対象となる
税務署の調査から逃れるために、海外に送金するほか、海外に資金を置いておくケースも散見されます。しかし、100万円を超える国際送金については金融機関が税務署に「国外送金等調査」という書類を作成する義務があるので((内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条)、海外送金や海外資産も調査の対象となります。
その他の資産から手許預金があるのが推認できることがある
手許預金は預金のみから推測するわけではありません。 手許現金が多い場合には、外国預金・債券・株式・FXなどの金融商品への投資をすることが多いからです。これらの資産が不自然に多い場合、手許預金を疑われる要因となるでしょう。
手許現金を申告しなかった場合に税務署から科されるペナルティについて
ここでは手許現金を申告しなかった場合において、税務署によって行われる税務調査と修正申告について紹介します。
申告漏れが疑われる場合は税務調査が実施される
タンス預金や相続開始直前引き出し預金など、申告漏れが疑われる動きがあった場合には税務調査の対象となります。引き出したお金の使い道を正確に答えられれば問題ありませんが、疑いをかけられてしまうと税務署による実地調査が行われることも少なくありません。
相続税の税務調査は大きく「強制捜査」と「任意調査」に分けられますが、基本的には「任意調査」となることがほとんどです。任意調査とはその名前の通り、納税者の同意を経て行われる調査を指します。とはいえ、事前に税務調査が入る旨の通知が届くものの、調査を拒否すると罰則が適用される恐れがあるので注意しましょう。調査では相続人に対して聞き取りが行われることに加え、被相続人の通帳や印鑑、家の中もにいたるまで隈なく捜査されることになります。また、「反面調査」と呼ばれる調査がなされることもあるでしょう。反面調査では取引先の金融機関(銀行や証券など)に対し、怪しい値動きがなかったかどうか税務羞悪による聞き出し調査がなされます。
税務調査の結果次第では修正申告や追微課税の対象となる
手許現金を隠していたことがわかった場合のペナルティには次のようなものがあります。
- 1過少申告加算税
- 2無申告加算税
- 3延滞税
- 4重加算税
- 5刑事罰
それぞれについて、見ていきましょう。
過少申告加算税
本来手許現金として申告すべきものをしなかったあるいは少なく申告した場合には、過少申告加算税が課せられます。
追納する税額によって、
- 追納する税額の50万円以内の部分:10%
- 追納する税額の50万円を超える部分:15%
の加算がされます。
無申告加算税
手許現金として隠していて相続税申告をしなかった場合には、無申告加算税が課されます。
- 本来納付すべき税額の50万円以内の部分:15%
- 本来納付すべき税額の50万円を超える部分:20%
の加算がされます。
延滞税
本来払うべき部分を支払っていないのであれば延滞税がかかります。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内の部分:年2.5%
- 納期限の翌日から2ヶ月を超えた部分:年8.8%
※(2021年1月1日から2021年12月31日までの間)
重加算税
無申告・過少申告の態様が悪質であると評価されると、重加算税が課せられます。
- 過少申告の場合:35%
- 無申告の場合:40%
の加算がされます。
刑事罰
相続税法違反については刑事罰が科される可能性もあります。
<脱税>
虚偽や不正行為で脱税をした場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が併科
<故意の申告書不提出>
期限内に申告書を提出せずに相続税を免れた場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科
<無申告犯>
正当な理由なく期限内に申告書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
申告漏れがわかったら自主的に修正申告をしよう
相続税の申告後に、申告を忘れた手許現金の存在が発覚した場合には、その時点で自主的に修正申告を行うようにしましょう。自主的に申告をすることにより、加算税が免除されます。
また、そもそも申告漏れが起きないように手許現金は他の資産と区別して記録しておくほか、なにか質問をされた場合に答えられるよう支払いの記録を残しておくことも大切です。
支払いの記録を残しておくことで税務署から必要以上の追求を受ける恐れがなくなるほか、他の相続人との間でのトラブルも起きにくくなります。
手許現金の申告に関する相談は税理士へ
このページでは、相続税における手許現金について、申告しないことができるのか、しなければどのようなペナルティがあるのかをお伝えしました。
税務署は多種多様な方法で資産を調べることができるので、手許現金を隠し通すことは難しいといえます。
税務署にばれると最悪のケースでは刑事罰となりますので、きちんと申告するようにしましょう。
なお、申告の仕方がわからない場合には、早めに税理士に相談するようにしてください。
沖田豊明 プロフィール

不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など